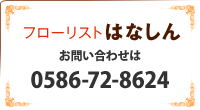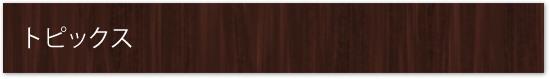「卒業式の花束・アレジメント」予約受付中
2011/2/24
 |
3月まじか春も近くにきている昨今ですが卒業・送別シーズンをむかえようとしています。おめでとうの中にお花はプレゼントの代名詞です・・ぜひお花を演出の場所にお使いくださいますよう・・おねがいします。 |
やる気???ことしは
2010/1/13
「やる気がある」「気丈に」「気合いをいれる」 「いい気をいれる」とか、「気配り」「気がつく」「気持ち」「気分がいい」とか、 なんとなく精神的なエネルギーみたいなものを感じさせますね。 そしてそれらは、生きていて活動している・から出てくるものです。 つまり、 体は、食べたものと、呼吸によって取り込んだ空気をもとに、さまざまな反応が行われてエネルギーを生み出し、これによって体内各所のいろいろなものが機能しています。 この基本的な動くエネルギーみたいなものを「気」と呼び、それが充実していて各所の連絡がスムーズに行われ機能している状態を「気がうまく流れている」といったりします。 やる気がでてくる・ |
七五三は…天気?
2009/11/9
11月15日は天気になるといいですね。旧暦の15日はかつては二十八宿の鬼宿日(鬼が出歩かない日)に当たり、何事をするにも吉であるとされた。また、旧暦の11月は収穫を終えてその実りを神に感謝する月であり、その月の満月の日である15日に、氏神への収穫の感謝を兼ねて子供の成長を感謝し、加護を祈るようになった。明治改暦以降は新暦の11月15日に行われるようになった。現在では11月15日にこだわらずに、11月中のいずれかの土日・祝日に行なうことも多くなっている。 3歳は髪を伸ばす「髪置(かみおき)」、5歳は初めて袴をつける「袴着(はかまぎ)」、7歳は、それまでの紐付きの着物に代わって、本仕立ての着物と丸帯という大人の装いをする「帯解(おびとき)・紐落(ひもおとし)」の名残りである。現代では行事に正装に準じた衣装(晴れ着)で臨み、洋服の場合もあるが和服の方が多い。少女(極稀に少年)は、この時に初めて化粧(厚化粧の場合が多い)をして貰う場合が多い。奇数を縁起の良い数と考えるようである。 |